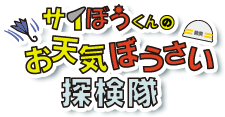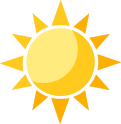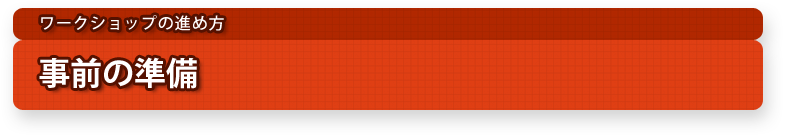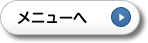1.ユーザー登録をする
- 指導者の方が「ぼうさいマップ」の管理者ユーザーの登録をしてください。
- 管理者ユーザーは、ユーザーを作成することができます。使用するタブレット数のユーザーを登録してください。
2.地域の防災情報を収集し、対象となるテーマを考える
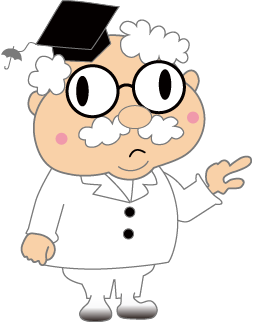
- 地域の気候や地形、発生しやすい災害など、地域の特性を
検証しましょう。 - 市町村などが作成したハザードマップを確認しましょう。
- 地域の町内会などが作成した防災情報が参考になることもあります。
- 地域で発生した過去の災害 についても確認しましょう。
- 雪の多い地域では、雪害をテーマに実施してもよいでしょう。
3.町歩きのルートを設定する
- 町歩きのルートは、あらかじめ指導者が設定しておいたほうが、進行がスムーズでしょう。
- チェックポイントについても、あらかじめ指導者が想定しておいたほうがよいでしょう。
- 小学校の周辺や通学路など、子どもたちが普段歩き慣れたルートにできると、身近な防災にも役立ちます。
- 自宅から避難所へのルートなど、テーマを決めてもよいでしょう。
- 実際にタブレット端末を使用しながら町を歩くと想定より時間がかかる場合もあります。途中でルートを短縮できるなど、柔軟な対応が可能なルートにしておくとよいでしょう。
- 車通りの多い道を避けるなど、ワークショップに適した環境かの確認も必要です。
4.説明資料を作成する
- 子どもたちの気づきに役立つような知識の説明が有効です。地域の気象特性、発生する可能性のある気象災害、過去に発生した災害などの説明資料を作成しましょう。
- 町歩きの注意点(車に気をつける、歩きながらタブレットを使用しないなど)も必要です。
5.スタッフを確保する
- 町歩きのサポートとして、1チーム(子ども3~5人)に大人2名以上が付き添うと安全です。1人は「ぼうさいマップ」作成やタブレット使用の指導、もう1人は車両などへの注意喚起をしてあげるとよいでしょう。
- 保護者の方々などにも、付き添いをお願いしてみましょう。
6.タブレット端末を準備する
- タブレットは、子ども1人1台を用意できることが理想ですが、難しい場合は数人のチームに1台でもいいでしょう。
- 保護者の方のスマートフォンでも使用できる機種があるかもしれません。補助端末として使用させていただく方法もあります。
7.その他の機材の準備
- パソコン、プロジェクター、ホワイトボードなど(町歩き前後のプレゼンテーション用)
- プリンター(作成した「ぼうさいマップ」を子どもたちの持ち帰り用に印刷することができます。)
- プリントアウトした地図(タブレットでも地図を見ることができますが、紙に印刷した地図もあると有用です。)
- デジタルカメラやビデオ(ワークショップの様子の記録用)
8.参加者に準備してもらうもの
- 筆記用具
- 帽子、水筒(特に夏場は熱中症対策が必要です。)
- 保護者の方のスマートフォン(「ぼうさいマップ」作りに利用できる可能性があります。)