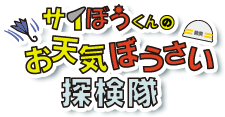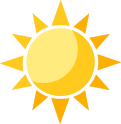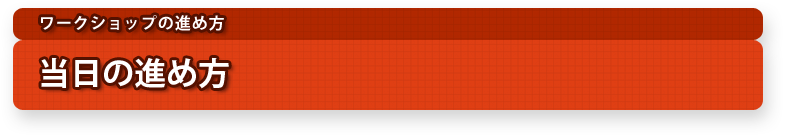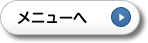事前レクチャー(15~20分)
様々な災害について
- 日本で発生する気象災害について説明し、災害から身を守ることの重要性を再認識してもらいます。
(動画 ワークショップ1) - 最近発生した災害を紹介すると、子どもたちの記憶にも新しく、興味を引きつけることができます。
(動画 ワークショップ2) - 地域で過去に発生した災害を紹介すると、災害を身近に考えてもらうことができます。
(動画 ワークショップ3)
町歩きのテーマとルートの確認
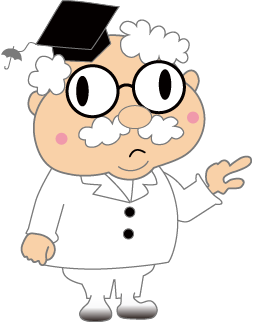
- 町歩きのルートを参加者で共有しましょう。
- 避難所へのルートなどテーマの設定がある場合は、テーマの意味を説明しましょう。
- ルートを「ぼうさいマップ」に登録することもできます。
チェックポイントのガイド
- 危険箇所、避難場所、役立つ場所など、チェックポイントを説明しておくとスムーズでしょう。
(動画 ワークショップ4) - ルートの地形や標高も確認し、気象災害との関連について説明すると良いでしょう。
(動画 ワークショップ5) - 市町村などが作成したハザードマップについても紹介し、危険個所を確認すると良いでしょう。
危険箇所は「ぼうさいマップ」に登録することもできます。
(動画 ワークショップ6)
チーム分け
- 用意できるタブレットの数と参加者の人数、スタッフの人数を考えて、チーム分けをします。
- 1チームにタブレット1台を用意する場合、1チーム3~4人くらいが適当でしょう。
- 高学年と低学年を組み合わせるなど、学年のバランスを考えてチーム分けを行いましょう。
町歩きの注意点
- 車に気をつける、歩きながらタブレットを使用しない、走ったり勝手な行動をしたりしない、仲良く実施するなど、安全に楽しく町歩きをするためのルールを確認します。
(動画 ワークショップ7)
町を歩いて「ぼうさいマップ」作り(50~60分)
- 子どもたちの歩くペース、作業するペースにあわせて、無理に急がせないようにしましょう。時間が足りなくなったら、途中でルートを変更するなど柔軟に対応しましょう。
- 気づいてほしいポイントについては、指導者がヒントを与えてあげることも方法ですが、なるべく自発的な気づきを引き出すような心配りも大切です。
- 夏場は、熱中症にならないように、こまめな水分補給を促し、作業時間が長くならないように配慮しましょう。
(動画 ワークショップ8)
発表・まとめ(20~30分)
- チームごとに町歩きで登録した内容を発表して、参加者で共有しましょう。
- 発表だけではなく、質疑応答や意見交換の時間も設けると、理解が深まるでしょう。
- 協力いただいた大人からも、意見や質問をいただくと、有意義でしょう。
- 作成した「ぼうさいマップ」は印刷して持ち帰ることができます。